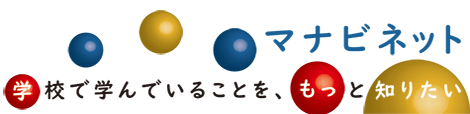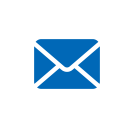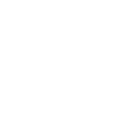【特集】
「国語」で考える探究学習の方法論
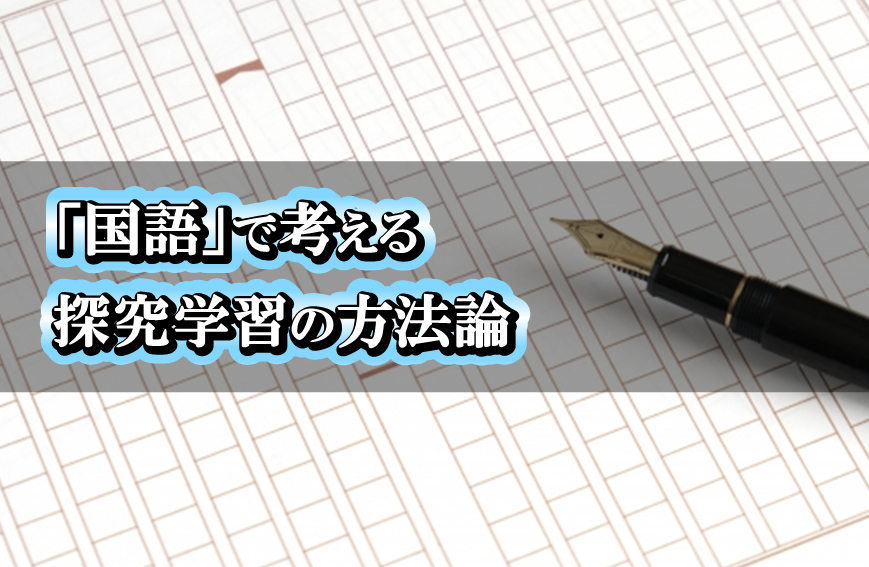
アルスコンビネーター・知窓学舎塾長・多摩大学大学院客員教授
矢萩 邦彦
探究とは、特定分野を掘り下げて行く営みである。なので当然、特定のテーマがあった方が、探究がしやすいということになる。そうすると主要教科の中では理科や社会にかたよりがちで、実際、私のところに寄せられる探究に関する相談も、国語や算数・数学をどのように探究的に扱うかというものが少なくない。そのなかでも、今回は「国語」という教科でいかに探究学習を実現するかについて考えてみたい。
「国語」は言語学なのかというと、そうではない。しかし、日本語学なのかというとそういうわけでもないし、日本語会話でもない。私たちは日常的に日本語を使っているが、それは国語力とは直結しない。英語圏では子どもも英語を使いこなしていることを考えればわかりやすい。ネイティブは文法や構文など意識しないまま母語を習得している。それは私たちにとっての日本語も同様である。
では改めて、国語とは何なのだろうか? まず教える側がそういう疑問を持ち、探究をはじめることが、国語の探究授業をつくって行く上で必要不可欠な条件だと言える。
大前提として、探究はテーマやコンテンツが重要なのではない。教える側が探究的な視点を持っていれば、なんでも対象として成立する。逆に言えば、探究的な姿勢のない教師に探究学習をナビゲートすることは、構造的にできない。テストに出るから学ぶのでは、国語の探究ではない。
国語探究を実践化する上で一つの指針となるのが、日常の中で獲得できる「国語」と、そうではない「国語」を分類することである。例えば、家族や友達との日常会話では、単語や文法がおかしくても通じてしまう。それで満足してしまうなら、そもそも国語を学ぶ目的を失ってしまうかもしれない。しかし、日常では足りない国語力とは何かを考えれば、あえて国語を探究する方針が立ち上がってくる。
私たちが国語を学ぶ理由の一つは、知らない誰かとコミュニケーションを取るためである。家族や友人間で適当な言葉でも通じてしまう理由は、お互いのことをよく知っているからに他ならない。つまり、特定のコミュニティ内ではあまり困らないが、一歩外へ出て、お互いのことを知らない状態になったら、たとえ同じ言語を使っていても、言葉の概念や文法や慣用表現が共有できていなければ、理解することは難しい。
正確な伝達と共感に「国語」という教科を学ぶ意味があるのだ。
中世のリベラルアーツにおいては、文法・論理学・修辞学の、いわゆる言語三科が特に重要視された。その理由はシンプルで、ちゃんと考えるために必要だったからだ。人間が理性的に、あるいは論理的に思考するためには言語が必須である。
もちろん、イメージの組み合わせによる思考も可能である。かのプラトンも、学園アカデメイアの入口には「幾何学を知らざるもの入るべからず」と掲げていたというから、その力は古来より重視されてきた。しかし、それは論理的になりにくく、何より伝わりにくい。
国語や現代文はその性質上、現代社会や哲学、文化人類学をはじめとした教養全般を扱う教科であると言える。それゆえ、文章の内容に深入りするような授業を散見する。それはそれで意味があるものだし、私自身、国語の教材で哲学や人類学に興味を持った経験もある。しかし、それでは国語という教科をメタ認知できているとは言えない。いかにして国語という教科を構造的に捉え、ツールとしてそれを使いこなすことができるかに国語探究の焦点を当てるべきである。そしてそれは、小学生や中学生に対してこそ重要であると考える。
国語自体を探究する視点として一例を挙げると、私が小学生から大学院生まで幅広く効果を確認しているものの一つに「助詞」の探究がある。近年、機能語という視点で語られることも多くなってきたが、日本語における助詞はひらがな1文字がまとう情報量が多い。例えば、
②ぼくはやります。
③ぼくもやります。
という3つの文にはどのような違いがあるだろうか。どれも自分のことしか話していないのにもかかわらず、自分以外の存在の動向が浮かび上がってくるだろう。
この違いを捉えつつ、背景を想像してシェアする。ひらがな1文字で伝わり方が変わることを体感すれば、探究すべきことは無限に見つかるのではないだろうか。

探究を取り入れる上で、最近になって問題定義されているのが「専門性なき探究はありえるのか?」という視点だ。主体性にフォーカスすると生徒任せになりがちなのだが、完全に生徒に任せると浅くなってしまい、誰でも言えるような問題点と抽象的な解決案を並べて、時間が終わってしまうこともしばしばである。
もちろん、指導しすぎてもうまくいかないのだが、近年の探究やファシリテーションは、指導する側の知識や経験が軽視される傾向がある。探究していくということは、一つのテーマを掘り下げて究めていく過程に意味がある。当然、ナビゲートする側に専門性があるからこそ、教育機関における構造的探究で、深みに導くことができる。私が運営する知窓学舎では、専門性を持つ実務家のみを講師として採用することでこの問題に対応している。
先日、文部科学省マイスター・ハイスクールに指定されている福井県立若狭高等学校へ取材で訪れた。そこで行われていた実践は、これからの探究を考える上で示唆に富むものであったので、3つのポイントに整理して紹介したい。
1つ目は、海洋科学科でありながら「恋愛」や「ドラえもん」などのテーマを用いて、グループで意見をシェアするという授業が行われていた。最初から専門性の高いテーマを扱うと、萎縮して意見を言えなかったり、コピペしたような意見が目立つ。あえて、誰でも意見が言いやすいテーマからはじめることで、セーフティーな場をつくりだしていた。これは探究の準備運動とも言えるが、そもそも目的を達成するためには「対話力」が必要である。国語の教科性を理解しているからこそ、カリキュラムの中でここに時間を割くことができるわけだ。
2つ目は、教師の関わり方である。探究活動においては、生徒と教師がフラットであることの重要性がフォーカスされがちだ。もちろん、ともに探究をする姿勢が大事なのは間違いないが、学校組織で構造的探究を行うのであれば、指導レベルである教師が生徒と一緒に楽しむことで効果が期待できる。生徒と同レベルの知識と経験では、「指導しない教育」はうまくいかない。指導できる人間が教え込むことを手放して、はじめて本質的なファシリテーションやナビゲートが実現する。
3つ目は、探究を引き継いでいく仕組みである。限られた時間で掘り下げて行くためには、毎回イチからスタートしたのでは、毎回似たようなところまでしか到達しない。先輩の探究を後輩が受け継いでいくことで、深みが増していき、より大きなプロジェクトを成功させることができる。若狭高校では、生徒のつくった鯖缶がJAXAの宇宙食に認定されたのだが、そこまで13年もかかっており、今なおプロジェクトが進んでいる。
これらの事例はそのまま真似することは難しいだろうが、例えば、以前の探究授業を実施した際に出た意見やプレゼンの内容などをアーカイブしておき、先にシェアして、そこから探究をスタートさせることで、毎回少しずつでも厚みや深みを出していくこともできる。
今回は国語探究について考えてみたが、結局は探究の本質をつかんでさえいれば、教科もテーマも関係なく授業にすることができる。担当教師は、まず柔軟な姿勢と、学ぶ意欲を持ちたいところだ。
矢萩 邦彦 氏
探究型教育・パラレルキャリアの第一人者。2万人を超える直接指導経験を生かし「すべての学習に教養と哲学を」をコンセプトに「探究×受験」を実践する統合型学習塾『知窓学舎』を運営。現場主義を貫きつつ、教育界に限らず多様な企業・組織で授業・研修・コンサル・監修顧問を務める。編著書、メディア出演も多数。著書に『子どもが「学びたくなる」育て方』(ダイヤモンド社)、『新装改訂版 中学受験を考えたときに読む本』(二見書房)、『正解のない教室』(朝日新聞出版)など。
■知窓学舎 http://chisou-gakusha.jp/
◆購読申込に関するお問い合わせはこちら
https://manavinet.com/subscription/
◆『塾ジャーナル』に関するご意見・ご感想はこちら
https://forms.gle/FRzDwNE8kTrdAZzK8
◆『塾ジャーナル』目次一覧
https://manavinet.com/tag/jukujournal_mokuji/